|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
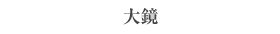 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 五十九代 宇多天皇
次の帝は、亭子の帝(宇多天皇)と申し上げた。このお方は、小松の帝(光孝天皇)の第三皇子である。母君は皇太后班子女王と申した。二品式部卿贈一品太政大臣仲野親王のご息女である。この帝は、貞観九年丁亥(867)五月五日にお生まれになった。元慶八年四月十三日に、臣籍に下り、源氏になられた。御年十八歳。仁和三年丁未(887)八月二六日に東宮に立たれ、そのまま同じ日に帝位につかれた。御年二十一歳。ご在位は十年。
|
|
|
|
若宮は格段に賢くて、臣下にするには惜しいが、親王にすれば世間の疑惑をこうむることになるし、宿曜(占星術)の賢者に占わせても同じことを言うので、皇子を臣籍に下ろして源氏の姓を与えることに決められた。
(桐壺) |
|
|
|
宇多天皇が源氏の姓を賜り臣籍に下ったのに、東宮に立ち、その日に帝位についたのに対し、物語の源氏は臣下のまま。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 太政大臣基経
基経は、陽成院が譲位なさった陣の座の公卿の評定に伺候なさった。その時、源融は左大臣という地位で、ご身分も尊く、天皇の位につきたい気持ちが強くて、
「どうして議論などする必要がある。天皇に近い血筋を求めるなら、融などもいる」
と言い出したのを、基経は、
「天皇の血筋であっても、一度源氏の姓を賜って、臣下として仕えたもので、天皇の位についた前例があるだろうか」
と申し出た。これは当然のことなので、この基経大臣の裁定によって、小松の帝(光孝天皇)が即位なさった。 |
|
|
|
帝はかねて考えていらっしゃった譲位のことをお漏らしになると、源氏の君は、目もあげられないほど恐ろしく思われて、
「そういうことは絶対にあってはなりません」
と申し上げて辞退なさる。
「故桐壺院のお気持ちは、多くの皇子たちの中でわたしに格別心をかけてくださりながら、位を譲ろうとは思ってもいらっしゃいませんでした。どうして、そのご遺志にそむいて、およびもつかない位につくことができるでしょう。わたしはただ、院の定められたとおりに、朝廷にお仕えして、もう少し年をとりましたら、出家して心静かに勤行の日々を過ごしたいと思っています」
と、いつもおっしゃていることを変わりなく申し上げられたので、帝はとても残念に思われる。(薄雲) |
|
|
|
源融の野心に比べ、物語の主人公、源氏はひたすら臣下にこだわる。主人公の人格化の美化。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 左大臣師尹
左大臣師尹が左大臣に転任なさったのは、西宮殿(源高明)が太宰権師に左遷されて筑紫へ下った代りである。流罪にいたる騒動(安和の変)は、この小一条(師尹)がざん言したせいだと、世間の人は噂した。そして、その年も過ごさないで亡くなられたのを、高明左遷の要因をつくった報いだろうと言っているようである。それも本当のことだろうか。
|
|
|
|
源氏の君は
「わたしの場合、遠国へ流罪に処すべきだという決定などもあると聞いていますから、特別に重い罪になるのでしょう。じぶんは潔白だとそ知らぬ顔で過ごすのも差し障りが多く、これ以上大きな辱めを受けないうちに世の中を逃れようと決心したのです」(須磨) |
|
|
|
事実との照らし合わせ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 太政大臣兼家
この殿(兼家)が法興院に出かけられるのを、
「気味の悪い所」
と、人々は同意しなかったのに、とてもおもしろい所だと思われて、人の言うことを聞き入れずに、出かけて行って、まもなくお亡くなりになった。法興院について殿は
「東山などがとても近く見えるのが、山里のような感じで、風情がある」
とおっしゃった。物忌のとき、法興院に出かけようとして、
「出かけるとしたら吉凶はどうか」
と占いをさせられたのに、その時、法興院で病気になられ、亡くなられた。
「馬屋の馬に随身を載せて、粟田口へ遣わしたのが、はっきりと遠くまで見渡せる」
などと、この屋敷を趣あるようにおっしゃり、月の明るい夜、格子も下ろさないで、眺めていらっしゃったところ、目に見えないものが、その格子をばたばたと全部下ろしてしまったので、お付の人々は恐れて騒いだが、殿は、少しも驚かず、枕元にあった太刀を引き抜かれて、
「月を見るために上げてある格子を下すとは、何者の仕業だ。まったくつまらないことを。元のように上げておけ、そうしないと、ひどい目にあうぞ」
とおっしゃったところ、すぐに格子は上げられたというように、だいたいにおいて安心できないことが多かった。 |
|
|
|
源氏の君は宵(午後十時頃)をすぎるころ、少しうとうとなさると、枕元にとても美しい女が座っていて、
「わたしがとても素晴らしい人と想っているのに訪ねようとも思わないで、こんなどうでもいいような女を連れてこられて可愛がられるとは、とても残念で悔しい」
と言って、隣で寝ている女をゆすって起こそうするのを夢でごらんになる。物の怪に襲われるような気がして、はっとして目を覚まされると、灯火も消えていた。不気味な感じがして、魔除けに太刀をひき抜いてそばに置き、右近を起こされた。(夕顔)
|
|
|
|
物の怪 怪異 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 太政大臣兼家
源宰相頼定の君が尚侍(綏子)のところへ通っているという噂が、世間に広がって、尚侍は里下がりした。さらに妊娠していると、(東宮の)三条院は聞かれて、今の入道殿(道長)に、
「そういうことがあるのは、本当なのか」
とお尋ねになったので、道長は
「行って確かめてきましょう」
と言って、(妹である)尚侍のところへ行かれると、尚侍はいつになく変に思われて、几帳を引き寄せて隠れようとなさるのを、几帳を押しのけてごらんになると、もともと華やかな顔立ちなのに、とても丁寧に化粧をしていらっしゃったので、いつもよりも美しく見える。
「東宮のところへお伺いしたら、これこれとおっしゃったので、様子を拝見に来たのです。噂が嘘なら、東宮に事実と聞かれたら、とてもお気の毒だから」
と言って、尚侍の胸を引き開けて、乳房をひねったところ、顔にさっとほとばしってきたではないか。道長はなにもおっしゃらないで、そのままお帰りなった。東宮のところへ行って、
「事実でした」
と報告して、なさった通りのことを申し上げると、東宮の三条院は、さすがに、もともと愛しいと思っていらっしゃった仲だったので、かわいそうに思われた。
「尚侍は、殿(道長)がお帰りになった後で、誰のせいでもないごじぶんの心からしたことなので、ひどくお泣きになった」
と、その時拝見した人が話してくれた。尚侍が東宮のおそばに仕えていた間も、宰相(頼定)は通っていらっしゃった。それがあまりにも噂になったので、東宮もお聞きになって、
「帯刀(東宮坊の官人)に命じて頼定を蹴飛ばさせてやろうと思ったが、亡くなった尚侍の父大臣(兼家)のことを思い出して、草葉の陰でもどんなに嘆かれるだろうと、愛しくなって、そうはさせなかった」
とおっしゃった。この過失によって、源宰相は、三条院の在位中は昇殿もできずに、地下の上達部でいらっしゃったが、今上帝(後一条天皇)になって昇殿を許され、検非違使の長官などになって、お亡くなりになった。
|
|
|
|
そのころ尚侍の君(朧月夜)が里(右大臣邸)に退出なさった。瘧病を長く患われて、まじないなども気がねなくしようというのである。修法などを始めて、すっかりよくなられたので、右大臣家ではどなたも喜んでいらっしゃるときに、例によってめったにない機会だからと、お互いに示し合わされ、無理な算段をして毎晩お逢いになる。尚侍の君は、今が女ざかりの、華やいだ感じの方で、その方が少し病にやつれてほっそりとなられたのが、とても美しい感じである。弘徽殿の大后も同じ邸にいらっしゃる時だったので、とても恐ろしい感じがするが、源氏の君はこういう無理な逢瀬ほどかえって心がはやる癖があるので、いくらこっそりと通っても、それが度重なれば、それに感づいてる女房たちもいるようだが、面倒なことにかかわりたくないので、弘徽殿の大后にはそれを話さない。(賢木)
「御息所は亡き東宮がとても大切な人として寵愛してたのを、そなたは並みの女のように軽々しく扱っているらしいが気の毒なことだ。斎宮もじぶんの皇女たちと同じように思っているから、いずれにしても御息所を粗略にしないほうがいい。心の荒びにまかせてこんなふうに浮気をしていては、当然世間の非難をこうむることになる」
などとご機嫌が悪く、源氏の君自身もその通りだと思われるので、かしこまっていらっしゃる。
「御息所に恥をかかせないように、いずれにしても穏やかに扱って、女から恨みを買わないようにしなさい」
とおっしゃるにつけても、あの道にはずれた大それたこと(藤壺との密通)を
〈もし院に知られたら?〉
と、そう思うだけでも恐ろしいので、恐縮して退出なさった。(葵)
※この場合、桐壺は源氏と六条御息所との関係を認めている。 |
|
|
|
親王、内親王(皇族)が想う人に対する密通への関心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 巻第二 花山たづぬる中納言
どうしたことか、こうしているうちに梅壺女御(詮子)がいつもと違って苦しそうにしていらっしゃるので、父大臣(兼家)はどうしたことかと恐ろしく思われたが、ご懐妊であった。世間の思惑もうるさいので、一、二カ月は隠しておかれたが、いつまでも隠しておくことではないから、三月目に奏上なさったところ、帝(円融)はとても喜ばれたにちがいない。
(中略)
梅坪女御が里下がりなさるのを、帝はとても不安でつらい気持ちでいらっしゃるが、宮中にとどめておくわけにもいかないので退出させられるが、その時の様子は言葉には言えないほどである。それ相応の上達部や殿上人がみな残らずお供に奉仕なさる。
|
|
|
|
宮中の掟があることなので、帝はいつまでも引きとめておくこともできないし、見送ってあげることもできないもどかしさをどうしようもなくお感じになる。とても華やかな美しい人が、すっかりやつれて、ひどく悲しみに沈んで、口に出して言うこともできないで、生死もわからないほど息も絶え絶えなのを帝はごらんになると、過去も未来も真っ暗で、いろいろなことを泣く泣く約束なさるが、更衣は返事もできないで、目つきもよほどだるそうで、ふだんよりいっそうなよなよして意識がもうろうとして寝ているので、帝は、
〈どうしたらいいのだろう〉
と不安にかられる。退出の輦車の宣旨などを伝えられても、また部屋にお入りになって退出させようとはなさらない。(桐壺) |
|
|
|
帝のエロスにおける幼児性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 正月に庚申の日があったので、東三条殿の院の女御(超子)の御殿でも、梅壺女御(詮子)の御殿でも、若い女房たちが
「年のはじめの庚申です。庚申待ちをなさいませ」
と申し上げると、それではと一同がその催しをなさる。この女御たちには同じ母親の男君が三人(道隆、道兼、道長)いらっしゃる。
「とても面白いことだ」
「素晴らしい」
「両方の所(超子と詮子の所)を行ったり来たりしているうちに夜も明けてしまうだろう」
などとおっしゃって、いろいろな遊びをしてみせられるが、和歌やなにやかや、たしなみ深い女房の様子をはじめとして、女房たちは碁や双六を競うのもおもしろく、
「この人たちがいらっしゃらなかったら、今夜の眠けざましにすることもなかったのに」
などと言ったり思ったりしているうちに、たびたび鶏が鳴く頃になった。院の女御(超子)は、明け方に脇息に寄りかかっていらっしゃって、そのままおやすみにってしまわれた。
「今頃おやすみにならなくてもいいのに」
などと女房たちが言うのを、
「鶏も鳴いたのですから、今はそのままに、起こさないように」
などと、女房たちが言っていると、これということもない歌を聞かせようとして、男君たちが、
「もしもし、お尋ねします。今になっておやすみになることもない。起きてください」
とおっしゃったのに、なんの返事もなくお起きにならないので、近寄って、
「もしもし」
と声をかけたところ、様子が普通ではないので、体を揺すってみるのだが、そのまま冷たくなっていらっしゃったから、驚きあきれて、灯を取り寄せてごらんになると、すでに亡くなっていらっしゃった。男君たちは
「どうしてこんなことが」
と言葉もなく思われて、殿(兼家)にまず
「これこれです」
と申し上げると、殿は呆然となって、うろたえながらその場に駆けつけてごらんになると、あまりにもひどいお姿なので、抱きかかえて転げまわるほど途方に暮れていらっしゃる。 |
|
|
|
紙燭を取って女をごらんになると、その枕上に夢に見た同じ顔の女が、幻のように見えてふっと消えた。
〈昔の物語なんかにこんなことは聞いたことがあるが〉
と、まったく異様なことで気味が悪いが、それよりもまず、この女が
〈どうなったのだろう?〉
と気が気でなく、わが身の危険もかえりみず寄りそって、
「おい」
と目覚めさせようとなさるが、もうすっかり冷たくなっていて、息はとっくに絶え果てていた。(夕顔)
左大臣家の邸内が人が少なくなって、ひっそりしていた頃、女君は突然、いつものように胸を咳きあげながら非常に激しく苦しまれる。宮中にいる人々に知らせるひまもなく、息が絶えてしまわれた。どなたも足が地につかない状態で退出なさったので、除目(任官)の夜だったが、こういうやむをえない病状の悪化のため、すべてがご破算になってしまったようである。人々は大声をあげて騒ぐが、あいにく夜中のことなので、比叡山の座主や、あちこちの僧都たちも呼び寄せることもできない。今はもう大丈夫だと安心していたのに、あまりにもひどい状態なので、左大臣家の人々は慌てふためいている。(葵)
|
|
|
|
死の場面への関心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 花山帝は、式部卿宮(為平親王)の姫君(婉子)がとても美しいと聞かれて、毎日手紙を寄越されるので、式部卿宮は
〈これほどの人を家に引きこもらせておくこともない〉
と思われて、支度を整えて入内させられる。故村上帝がとても大切に可愛がっていた四の宮(為平親王)が源師(高明)の娘に生ませた姫君で、ご両親の仲も高貴で素晴らしく、姫君もとても美しいのを、あらん限りのことをして入内させたのだから、今のところ大変なご寵愛を受けられ、入内の甲斐もあって素晴らしいことである。
今はこの程度で我慢なさればいいのに、帝はさらに、
「朝光の大将の姫君(姫子)入内なさい」
と、性急におっしゃるので、大将はどうしようかとためらっていたが、
〈東宮(懐仁親王)はまだ五歳で幼いし、女御更衣として入内させるなら花山帝へ参上させるのがいいだろう、誰も姫君を疎かには扱うはずがない〉
と意を決して入内させられる。
(中略)
こうして女御(姫子)が入内なさると、帝は見苦しいほどご寵愛なさる。それまで時めいていらっしゃった宮の女御(婉子)は、寝所の奉仕も、最近では圧倒されていらっしゃる。宮の女御は、
〈困ったことを〉
と、なんとなく嫌に思っていらっしゃるうちに、一か月ばかりの間、新女御(姫子)は絶えず帝のそばに参上なさり、帝も姫子の部屋に行かれたりして、ほかに女御は誰もいらっしゃらないようなおもてなしである。
(中略)
そのまま日を過ごしていらっしゃるうちに、閑院の大将殿(朝光)の女御(姫子)の寝所の奉仕がなぜか途絶えがちになり、最後には、
「寝所へ来なさい」
という言葉も思いつかれなくなった。ちょっとした手紙などもすっかりなくなって、ひと月二月が過ぎてゆく。
〈なんということだ、どうなってしまったのだろう〉
などと、大将はあれれこれ悩んでいらっしゃるがどうしようもなく、物笑いになる情けないありさまで、同じ宮中にいる人のようには思われないようになったので、しばらくはともかく、人目も恥ずかしく、どうしようもなく宮中を退出なさるが、帝は女御(姫子)のこうした出入りさえ関心をしめされなかった。驚きあきれる情けないこととして、世間では今この噂で持ちきりである。大将殿(朝光)も、
「参内すれば胸が痛む」
と言って、邸に閉じこもってしまわれた。世間では話のたねにしている。
「継母の北の方(延光室)がなにかなさったのではないか」
とまで、世間では言ったり思ったりしている。帝がお通りになる打橋などに誰かがなにかを仕掛けたのだろうか、女御(姫子)も参上なさらず、帝も女御のところへ出かけられず、見た目にもいたわしく奇妙な形で退出なさったから、その後は、そういうことがあったという痕跡もない。 |
|
|
|
先の帝の四の宮で、お顔だちがことのほか美しいと評判の、母后もこの上なく大切に育てていらっしゃる方を、帝に仕えている典侍は、先の帝の時から仕えている人で、母后の御殿にも親しく出入りしていたので、四の宮をご幼少の時から拝見していて、今もちらっと拝見して、
「お亡くなりになった御息所(更衣)にお顔が似ていらっしゃる方を、三代の帝にお仕えして、お見かけすることができなかったのですが、この后の宮の姫宮だけはとてもよく似たお姿でご成人なさっています。世にもまれな美しい方で」
と申し上げると、帝は、
〈ほんとうだろうか〉
と心をとめられて、丁重に入内を要請なさった。(桐壺)
更衣のお部屋は桐壺である。帝が大勢の女御や更衣の部屋を素通りしてしばしば桐壺へ行かれるので、女御たちがいらいらなさるのももっともである。更衣が参上なさるときも、あまり度重なるときは、打橋や渡り廊下のあちこちの通り道に汚物などをまき散らして、送り迎えの女房たちの着物の裾を台無しにしてしまい、また、ある時には、どうしても通らなければならない廊下の戸を閉めて閉じ込め、こっちとあっちでしめし合わせて辱めたり困らせたりすることも多かった。(桐壺)
|
|
|
|
女御たちの帝の寵愛を競う関係 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 村上帝などは、十人二十人の女御、御息所がいらっしゃったが、寵愛の深い方も浅い方も、普通に情愛があって、特別にある方を贔屓になさることはなかったのだが・・・・・・ (花山帝との比較) |
|
|
|
源氏の君はどんな女の場合でも、気持ちが安らぐ時がなく苦しんでいらっしゃる。長い年月が経っても、こんなふうに、一度でも逢った女には情愛を忘れられないので、かえって多くの女たちにとっては悩みの種になるのである。(花散里) |
|
|
|
事実の抽出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 女御(忯子)が懐妊なさった。とても心配なことに、ちょっとした果物もお口になさらない。花山帝はただ
「まず第一に弘徽殿にあげなさい」
とばかりおっしゃるので、ご寵愛の深さは素晴らしいのだが、大納言ははたで苦々しく思っている。三月になって帝に奏上して退出なさろうとするが、帝はあれこれ言ってお止めになるので、五カ月くらいになって退出なさる。
(中略)
帝は女御のことが気がかりで恋しく思われて、
「せめて宵の間だけでも」
とばかりおっしゃるが、大納言殿としてはとてもその気になれないでいたところ、女御もさすがに帝のことを気がかりに思っていらっしゃるので、大納言殿は、ほんの一日二日と決めて参内させられる。弘徽殿に参上なさるというので、部屋を整えたりするのを、ほかの女御に仕える女房などは、
「不吉な縁起でもないこと」
と言っている。
こうして女御が参内なさったので、帝はしみじみと嬉しく思われて、夜も昼もそのまま食膳にもつかれずお部屋に入っておやすみになった。
(中略)
こうして三日後に、退出させようと、迎えの人々や、車を差し向けたが、帝はまったく許されず、
「もう一晩、もう一晩」
と、留めていらっしゃるうちに、七、八日になったので、物忌も家を離れていては不安なので、大納言がその旨を誠実に申し上げたので、帝は泣く泣く退出を許されたが、輦車を引き出して退出するまぎわまで、お見送りに出て立っていらっしゃった。
(中略)
一条殿(為光)の女御(忯子)は、この数ヶ月なんとか小康を保っていたが、今回退出なさってからは頭も上げられず、驚くほど重体になられて、死を待つばかりの様子である。大納言は泣く泣くあれこれ心を悩ませていらっしゃるが、その甲斐もなく、懐妊後八ヶ月でお亡くなりになった。 |
|
|
|
その年の夏、更衣がちょっとした病を患って、実家に帰ろうとなさったが、帝は里下りもお許しにならない。ここ数年、病気がちだったので、帝はそれを見慣れていて、
「もうしばらく様子をみては」
とおっしゃっているうちに、更衣は日に日に重くなって、わずか五、六日のうちにひどく弱ってくるので、更衣の母君が泣く泣くお願いして退出させられた。 帝は、
〈このままで、とにかくなりゆきを見届けよう〉
と思われるが、更衣の母君が、
「きょうから始める祈祷(きとう)など、それなりの験者(げんざ)たちが承っていて、それが今夜から」
とせきたてるので、帝はしかたなく退出をお許しになる。
帝は胸がつまって、少しも眠れないで、夜を明かしかねていらっしゃる。見舞いの使者が行き来する時間でもないのに、しきりに気がかりな気持ちを漏らしていらっしゃったが、
「夜中過ぎに、お亡くなりになりました」
と言って里の者が泣き騒ぐので、使者も気を落として宮中に帰参した。(桐壺) |
|
|
|
帝のエロスにおける幼児性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 寛和二年(987年)六月二十二日の夜、突然帝の姿が見えなくなり大騒ぎである。宮中の大勢の殿上人、上達部、身分の卑しい衛士、仕丁にいたるまで、残る所なく火を灯して、隅々まで探したが、どこにもいらっしゃらない。
(中略)
山や寺を手分けして探すが、どこにもいらっしゃらない。女御たちは涙を流していらっしゃる。
「ああ、なんということ」
と嘆き悲しんでいるうちに、夏の短夜も明けて、中納言や惟成の弁などが花山を尋ねて来られた。そこに目もまるまるとした小法師の恰好で帝が畏まって座っていらっしゃるではないか。
「ああ、悲しい、なんということを」
と伏し転んで中納言も法師になった。惟成の弁も出家なさった。 |
|
|
|
尼君には、詳しくは書かず、ただ、
「三月の十四日に、草の庵を出て深い山に入ります。生きていても役に立たないこの身は、熊や、狼にでも施してやりましょう。あなたはやはり望みどおりに(皇子の)御世になるのを見届けてください。極楽浄土で、またお会いしましょう」
とだけ書いてある。
尼君は、この手紙を見て、入道の使者の僧にたずねると、
「この手紙を書かれて、三日後に、入道は、あの人も通わない山奥にお移りになりました。私どもも、お見送りに、ふもとまでは行きましたが、入道は皆お帰しになって、僧一人と童二人だけをお供に連れて行かれました。もはやこれまでと出家された時が、悲しみの最後と思っていましたのに、さらにこんな悲しみが残っていたのです。長年の間、勤行の合い間に物に寄りかかって弾いておられた琴の琴と、琵琶を持ってこさせて、弾き鳴らし、仏に別れを告げてから、お寺に寄進されました。そのほかの物も、多くはお寺に奉納されて、その残りを、弟子たち六十人あまり、親しい者だけがお仕えしていたのですが、身分に応じて分配され、さらに残っているものを、京の方々(明石の君や尼君)のためにお送りになりました。これが最後とお籠りなって、あのような遠い山の雲や霞の中に入ってしまわれたので、主人のいない空しい邸にとどまって悲しんでいる者が大勢います」(若菜上)
|
|
|
|
時事的事件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 巻第三 さまざまのよろみび
摂政殿(兼家)の五郎君(道長)は、三位中将で、容姿をはじめ、気性なども、兄君たちをどう思っていらっしゃるのか、うって変って、いろいろと優れていて男らしく、道心もあり、じぶんに心を寄せる人などに、特に目をかけて庇護なさった。人柄は人並み以上で、申し分のないお方である。后宮(詮子)も、特に心を寄せられて、実の御子とおっしゃって、特別になにごとにおいてもご配慮なさる。現在二十歳ほどでいらっしゃるが、冗談にも浮気っぽいところはない。といって生真面目というわけではないが、
〈人に恨まれたり、女から情け知らずと思われるのはじぶんにとっても辛いだろう〉
と思われて、並一通りの気持ちではない人には、人目に立たないよう言葉をかけていらっしゃった。 |
|
|
|
源氏の君は実際は、非常に世間に気がねして誠実にふるまおうとなさっていたから、艶っぽいおもしろい話などなく、交野の少将(物語の好色な主人公)からは、笑われてしまうだろう。
源氏の君がまだ中将(近衛府の次官)であった時は、帝のそばにばかり控えていらっしゃって、左大臣家にはまれにしか行かれない。
〈忍ぶの乱れや(恋ゆえの乱れではないか〉
と左大臣家の女房たちに疑われることもあったが、そんな色っぽいありふれた唐突な色事などは好まれない性質で、ただまれには、うってかわってひたむきに恋の限りをつくさなければならないと思いつめるくせが生憎とあるお方なので、不都合な行動をなさらないわけでもなかった。(箒木) |
|
|
|
主人公源氏の人物像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 三位中将殿(道長22歳)は、土御門の源氏の左大臣殿(雅信)の姫君お二人、この姫君たちは正室の子でとても大切に育てられて、将来は后にと思っていらっしゃる方を、どういうつてがあっただろうか、この三位殿が、その一人(倫子24歳)を
〈どうにかして妻にしたい〉
と、深く想われて、その気持ちを先方におっしゃった。だが左大臣殿(雅信)は、
「ばかげている。もってのほかだ。誰が、あのようなくちばしの黄色い青二才を出入りさせるというのだ」
と言って、まったく聞き入れなかったのを、母上は普通の女性と違っていて、賢く才気があるお方で、 「どうして、あの君を婿にしないことがあるでしょう。時々、物見などに出かけて見ているのですが、あの君は並々ではないと見えます。ここはわたしに任せてください。この話は悪いことではありません」
とおっしゃるが、殿は、
〈まったくとんでもないこと〉
と思っていらっしゃる。 |
|
|
|
内大臣は帰りの道すがら、
〈若君との結婚はそれほど不相応なことではないが、世間はいとこ同士のありふれた結婚だと思って、賞賛も羨望もしないだろう、源氏の君が、強引に弘徽殿の女御を押さえ込まれたのが辛くて、
《ひょっとして、この姫君を入内させたら勝てるかもしれない》
と期待していたのに、癪にさわるな〉
と思われる。源氏の君との仲は、だいたい、昔も今も良好でありながら、ただこういう権勢の面では、競い合われたしこりが残っていて それを思うと、面白くないので、目覚めがちに夜を明かされる。
「大宮だって、二人の仲はお気づきのはずなのに、またとなく可愛がっておられる孫たちなので、放任しておられたのだろう」
と、女房たちの言ってたのを思うと、ひどく憎らしく、ますます腹が立ってきて、多少勝気で物事のけじめをはっきりさせたい性格なので、怒りを静めることができない。(少女) |
|
|
|
時事的事件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 巻第六 かかやく藤壺
姫君(彰子)のご様子は今さら言うまでもないが、髪は、身の丈に五、六寸ほど余り、容貌(かおかたち)は言いようもなく美しく、まだとても幼い年齢(12歳)なのに、少しも幼いところがなく、言葉にできないほど素晴らしいご様子である。おそばに仕える人々も、姫君があまりにも若いので、
〈とても見栄えがしないのではないか〉
などと思っていたが、驚くほど大人びていらっしゃる。すべて前例のないほどの支度で入内なさる。
(中略)
このお方(彰子)は藤壺にいらっしゃるが、部屋の調度も、いくら光り輝く玉でも少し磨いただけではその光も薄いだろうが、この部屋はきらきらと照り輝いて、女房も普通の人ではおそばにお仕えすることもできないほど見事に設えていらっしゃる。
|
|
|
|
四の宮を入内させられる。藤壺と申し上げる。ほんとうに容貌や姿が不思議なほど更衣に似ていらっしゃる。この藤壺という方は、身分も高く、そう思って見るせいかとても素晴らしく、どなたも蔑むことはできないから、なんの気がねもなく何一つ不足もない。(桐壺)
女の子は顔つきがとても可愛らしく、眉のあたりがほんのりとして、子供っぽくかき上げている額や、髪の生えぎわがたいへん可愛らしい。
〈成長していくのが楽しみだな〉
と源氏の君はじっとごらんになる。それは、限りなく想っている人(藤壺)にとてもよく似ているからで、
〈しぜんに惹きつけられてしまう〉
と思われると涙がこぼれる。(若紫)
「箏の琴は、中の細緒が切れやすいから面倒だ」
と、低い調子の平調に下げて弾いてみられる。曲の出だしだけを弾かれて、琴を姫君のほうへ押しやると、姫君はいつまでもすねているわけにもいかず とても見事に弾かれる。まだ小さいので、体ごと腕を伸ばして弦を押さえて響かせる手つきがとても可愛らしいので、源氏の君も愛おしくなって、笛を吹き鳴らしながら教えてあげられる。姫君はとても賢くて、むずかしい調子なども、ただ一度で習得してしまう。なににつけても利発で優れた姫君の気性を、
〈これで願いがかなう〉
と源氏の君は思われる。(紅葉賀) |
|
|
|
人物像(藤壺、紫の上の容貌や性格の描写) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 帝(一条)は、今二十歳くらいでいらっしゃるようである。同じ帝といっても、
「さあ、どうだろう」
と未熟で物足りないところがある方もいらっしゃるものだが、この帝は、容貌をはじめとして、並はずれて清らかで美しく驚きあきれるほどのお方である。お酒などは多少お召し上がりになる。笛をなんともいえぬ美しい音色で吹かれるので、おそばにお仕えする人々も
〈素晴らしい〉
と感動して拝見している。女御(彰子)がまだ打ち解けないご様子なので、
「この笛をこちらを見てごらん」
とおっしゃると、女御殿は、
「笛は音色を聞くものですが、見るようなことがあるのですか」
とおっしゃって、お答えになるので、帝が
「だからあなたは、まだ子供。七十の年寄りの言うことを、そんなふうにおっしゃるのだから。ああ、恥ずかしい」
と冗談をおっしゃるご様子も、おそばの人々は、
「なんて素晴らしい。この世のめでたいことは、わたしたちがこうして宮仕えしている以外にはないでしょう」
と、言ったり思ったりしている。どんなことも肩を並べる人もないご様子でいらっしゃる。 |
|
|
|
源氏の君は、青海波(雅楽の曲名)を舞われた。相手をつとめるのは左大臣家の頭中将で、顔立ちも態度も人より秀でているが、源氏の君と並んでは、やはり桜の花のかたわらの深山木のようである。西に傾く陽光が鮮やかに射してきて、楽の音が高鳴って、興もたけなわの頃、同じ舞でも源氏の君の足拍子や表情は、世にまたとないほど素晴らしい。(紅葉賀)
翌年の二月に、東宮の元服の儀式がある。東宮は十一歳になられるが、年齢のわりには大きく大人びた清々しさで、源氏の大納言の顔をそっくり写したように見える。お二人が眩いほどに光り輝いていらっしゃるのを、世間の人々は素晴らしいことだと言うが、母宮(藤壺の尼宮)は、まったくいたたまれない気持ちで、今さらどうにもならないことに心を痛めていらっしゃる。帝も東宮を素晴らしいとごらんになって、帝の位をお譲りすることなどを、やさしく話して聞かせられる。(澪標)
|
|
|
|
人物像(源氏や冷泉帝の容貌や雰囲気の描写) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 巻第七 とりべ野
長保二年十二月十五日の夜になった。帝(一条)もお聞きになったので、
「(定子は)どんな様子だ、どんな様子だ」
とお見舞いの使者がしきりに訪れる。こうしているうちに御子がお生まれになった。女でいらっしゃったのが残念だが、ともかく安産だったのをなによりと思って、今は後産のことが心配である。地に額をつけて、騒がしく祈り、あれこれ誦経の布施を出して祈祷させたが、薬湯をさしあげても(定子は)お飲みになる様子もないので、誰もみなうろたえ迷っているうちに、ずいぶん長い時間が経つので、やはりとても心配なことである。
「灯を近くに持って来い」
とおっしゃって、(兄の)帥殿(伊周)が顔をごらんになると、ただならないご様子である。驚いて体をさぐってみると、すでに冷たくなっていらっしゃった。
「ああ、大変なことになった」
とあわてて、僧たちはうろうろして、それでも誦経を絶え間なく続け、部屋の中でも外でも額をつけて大声で祈るが、何の甲斐もなく亡くなってしまわれたので、帥殿は亡骸を抱かれて、声も惜しまずお泣きになる。
|
|
|
|
左大臣家の邸内が人が少なくなって、ひっそりしていた頃、女君は突然、いつものように胸を咳きあげながら非常に激しく苦しまれる。宮中にいる人々に知らせるひまもなく、息が絶えてしまわれた。どなたも足が地につかない状態で退出なさったので、除目(任官)の夜だったが、こういうやむをえない病状の悪化のため、すべてがご破算になってしまったようである。人々は大声をあげて騒ぐが、あいにく夜中のことなので、比叡山の座主や、あちこちの僧都たちも呼び寄せることもできない。今はもう大丈夫だと安心していたのに、あまりにもひどい状態なので、左大臣家の人々は慌てふためいている。(葵) |
|
|
|
死の場面への関心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 こうして十月に詮子の四十の賀がある。土御門殿(道長の本邸)で催された。行幸などがあり、誠に盛大な行事である。屏風の数々の歌は、この道の名手たちが詠んで差し出した。
(中略)
舞人は一家の公達である。賀の終わりのころに、殿のご子息のお二人が童(わらわ)舞(まい)をなさる。高松殿(明子)のお生みになった巌君は「納蘇利」を舞われる。土御門の様子は眺めも広々として風情がある。築山の木々はすべて紅葉し、中島の松にからみついている蔦の色を見ると、紅や蘇芳色の濃いのや薄いの、青色黄色など、さまざまな色の艶々した布きれなどを作ったように見えるのは、なんとも素晴らしい。池の上に同じ色のさまざまな紅葉の錦が映って、水が鮮やかに見えてとても美しいところへ、その色々の錦の中から現れ出た船の上で演奏する音楽を聞くと、ぞくぞくするほど素晴らしく面白い。すべてが口にしたり筆にしたりできないほどの、いろいろな趣向が尽くされていた。
中宮(彰子)は西の対にいらっしゃり、女院(詮子)は寝殿にいらっしゃるので、帝も東廂(ひがしびさし)の南面(みなみおもて)にいらっしゃる。殿の上(倫子)は東の対にいらっしゃって、上達部などは渡殿に着座していらっしゃる。諸大夫、殿上人などは庭に設けた小屋に着座している。女院の女房たちは寝殿の西南の渡殿に控えている。御簾の下からこぼれる女房たちの出衣などがとても美しい。
|
|
|
|
十月の二十日過ぎの頃に、六条院に冷泉帝の行幸がある。紅葉の盛りで、興趣も深いはずの行幸なので、帝から朱雀院にもお誘いの案内があって、院までお越しになるので、世にもまれな めったにない盛儀ということで、世間の人も心をときめかしている。主人側の六条院でも、心を尽くして、まばゆいほどの準備をされる。
午前十時頃に行幸があり、まず馬場殿に、左右の馬寮の馬を引いて並べ、左右の近衛府の武官が並んで立った作法は、五月の節句の競射の儀式と区別がつかないほど似ている。午後二時を過ぎる頃に、南の町の寝殿に移られる。帝の通り道の反橋や、渡り廊下には錦を敷き、外からあらわに見えそうな所には絵を描いた幔幕を引いて、厳重に設営してある。東の池に船を何艘か浮かべて、宮中の御厨子所の鵜飼の長と、六条院の鵜飼とを呼ばれて、鵜を放たれる。鵜は小さな鮒を何匹かくわえている。特別にご覧にいれるわけではないが、帝がお通りになる時に興をそえるために用意してある。築山の紅葉はどの町も見劣りすることなく美しいが、中宮の西の御殿の紅葉は格別なので、南の御殿と仕切ってある廊下の壁を崩し、中門を開けて、さえぎるものなく南の御殿から見渡せるようにしてご覧にいれる。帝と朱雀院の立派な席を二つ用意して、主人の源氏の君の席は一段下げてあったのを、帝のお言葉によって同列に直させられたのは、素晴らしく思えたが、それでも帝は決まり以上の礼を尽くしてあげられないのを残念に思われる。(藤裏葉)
六条院の南の御殿の西の一部分に源氏の君の御座所を用意する。屏風や、壁代をはじめとして、すべて新しいものと取り替えられる。格式ばった椅子などは立てないで、地敷(縁取りのあるござ)四十枚、褥、脇息など、すべて祝賀のための調度類は、とても美しく整えられる。螺鈿の御厨子を二揃いに、衣装箱を四つ置いて、四季の装束、香壺、薬の箱、硯、泔坏(ゆするつき 洗髪用の水を入れる器)、髪上げの箱などといったものは、目立たないところまで華麗に作ってある。挿頭の花を載せる台は、沈や、紫檀で作って、珍しい模様を彫り、同じ金具でも、色を使いこなしてあるのは、趣があり現代的で、尚侍の君(玉鬘)は、風雅の趣味が深く才気のある方なので、目新しい趣向を凝らしていらっしゃる。全体的なことは、大げさにならないようにしてある。(若菜上)
|
|
|
|
四十賀などの習俗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 巻十二 たまのむらぎく
殿(道長)の長子、大納言殿(頼通)を、今は左大将と言う。帝は物の怪がともすると起こるのを、とても恐ろしく思われて、皇后の娘女一の宮(当子)は斎宮でいらつしゃるが、女二の宮(禔子)は幼少の時から格別に可愛がっていらっしゃったから、ごじぶんさえ落ち着いて位を保っていらっしゃるなら、どのようにでもしてあげられるが、
〈どうかすると今日明日のうちに退位ということになるかもしれない〉
と心細くなられるので、
〈なんとか二の宮のためにふさわしい縁組を〉
と思われても、さしあたって適当なことも考えつかないので、
〈大殿(道長)の大将(頼通)などに預けようか。大将の北の方は中務宮(具平親王)の娘だが、それはどれほどのことでもないだろう。いくらなんでも二の宮には勝てない。それにわたしがこのように皇位にあるのだから、大将もいい加減にはできないだろう〉
と、その気になられて、大殿(道長)が参上なさったときに、こういうお考えがあることをおっしゃると、殿は、
「とにかくなにか申し上げることでもありません」
と、とても恐縮して、退出なさり、大将殿をお呼びになって、
「これこれのことを帝が仰せになったので、なにも言わず恐縮して退出してきた。さっそくそれ相応の用意をして、降嫁の日を仰せになった時に、参上すればいい」
とおっしゃると、大将殿は、
「どのようにでも」
とおっしゃって、ただお目に涙が浮かんでいるのは、北の方(隆姫)をとても大切に思っていらっしゃるのに、この降嫁のことはおそらく逃れることができないのを、残念に思われるからだろう。大殿はその大将の様子をごらんになって、
「男が妻一人しか持たないのは、ばかげたことだ。今まで子もいないのだから、とにかく子をつくることを考えろ。この皇女は子を生んでくださるだろう」
とおっしゃると、大将は恐れ入ってお立ちになった。
大将殿は自邸にお帰りなって、北の方をごらんになると、とても見事に飾りつけた御帳(みちょう)台(だい)の前に、低い几帳を引き寄せて座っていらっしゃる。衣の裾に髪がたまっているのが、几帳のそばから見える様子は、まったく絵に描いたようである。
〈女二の宮の髪の様子は知らないが、気品ある気後れするような高貴な点では、この人に優ってはいない〉
と、心の中で思われて、いつもりやさしくお話しになるが、気を許されない応対は、(高貴な女性だから)いつものことながら、
〈降嫁のことをそれとなく聞かれたのだろうか〉
と、やましさに心苦しくなられて、人知れず胸を騒がせていらっしゃるのも、実に男らしくない心である。それも北の方への深い愛情のあらわれだろう。 |
|
|
|
新婚三日の間は、源氏の君が毎夜欠かさず女三の宮のところへ通われるので、紫の上は今までこんな経験がないので、この辛さに耐えてはいるがやはり無性に悲しい。源氏の君の着物などに、一層念入りに香を薫きしめたりさせながら、ぼんやり物思いに沈んでいらっしゃる紫の上の様子は、とても可憐で美しい。源氏の君は、
〈どんな事情があるにしても、どうして、紫の上のほかに妻を迎える必要があったのだろうか。わたしの浮ついた情にもろいせいで、こんなことになってしまった、まだ若いにしても、誠実な中納言(源氏の子息)を朱雀院も婿にとは考えられなかったようなのに〉
と、じぶんながら情けなく思い、涙ぐまれて、
「新婚三日目の今夜だけは仕方がないと許してくれるだろうね。これから後あなたと夜一緒にいないようなら、じぶんながら愛想が尽きるだろう。かといって女三の宮を疎かにしたら、朱雀院はどう思われるだろう?」
と悩んでいらっしゃる心の中は苦しそうである。紫の上は少し微笑んで、
「ごじぶんでも、決めかねていらっしゃるのに、ましてわたしなどが仕方がないかどうか、わかるわけがありません」
と、冷淡に相手にもされないので、源氏の君は恥ずかしい気持ちがして、頬杖をついて横になられると、紫の上は硯を引き寄せて、
目に近く 移ればかはる 世の中を 行く末とほく たのみけるかな
(変れば変る男女の仲なのに 行く末長くと あなたを あてにしていたとは)
古歌なども一緒に書いてあるのを、源氏の君は手にとってごらんになり、なんでもない歌だが、なるほど、もっともだと思われて、
命こそ 絶ゆとも絶えめ さだめなき 世のつねならぬ なかの契りを
(命は絶えるときには絶えるが この無常の世とは違い わたしたちの縁は絶えることがない)
と書かれて、すぐには女三の宮のところへ出かけられないのを、紫の上に、
「出かけられないのでは、わたしが困ります」
と急きたてられるので、源氏の君は糊が落ちて柔らかくなった風情のある着物になんともいえない良い匂いをさせて出かけられるが、そんな源氏の君をお見送りするにしても紫の上の心中は穏やかではないだろう。
|
|
|
|
婚姻習俗
一夫多妻的習俗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 こうしているうちに、どうしたことなのか、大将殿(頼通)はこのところ気分がすぐれずとても苦しまれる。風病ではないかと、湯治をなさったり、朴(ほう)を召し上がったりして、
「読経の僧たちは番を欠かすことなく奉仕するように」
などとおっしゃって、明尊阿闍梨が毎晩夜通し加持をするが、病気はいっこうによくならず、ますます重くなられる。
(中略)
〈どんな様子だろう〉
と思っていらっしゃるうちに、早くも貴船の神が現れた。
「どうしてこんなことになったのだ。この大将殿は浮ついたことなどなさらなかったのに」
とよく調べてみると、あの帝から降嫁のご意向があったのがもとで、北の方(隆姫)の乳母などが、神に祈ったところ、しぜんと神の心にも感応なさって、このように大将殿を悩ませたのである。北の方は聞きづらいことに思われるが、どうするわけにもいかない。大殿(道長)は、
〈まったく情けない、困ったものだ〉
とお聞きになって、
〈どうしたらよいのか〉
と思っていらっしゃるうちに、大将殿はただ息も絶えるほどになられるので、数々の祈祷、読経、修法を、あちこちの祈祷層たちが集まって加持して、さまざまに騒ぎ立てるが、驚きあきれるほどの容態なので、殿の上(倫子)もどうしてよいかわからず、急いで大将の邸に行かれる。
(中略)
大将殿は重態と見えるので、殿の上(倫子)が殿に顔を近づけて涙を流していらっしゃると、殿(道長)は、
「長い年月崇めてきた法華経、助けてください。この人間世界に仏道を広めていらっしゃるのは、多くはわたしがそのようにしてさしあげたからです。せめてこの時に効験を拝見しないのでは、ご恩を頂かないのでは、いつ期待したらいいのでしょう」
と言い続けられて、泣きながら寿量品を読誦なさると、大将殿は急に体を動かされ、せせら笑っていらっしゃる。殿はますます涙を流して一心に法華経を読誦していらっしゃる。おそば近くに仕える女房で、ふだんはそういうこともなかった者に、物の怪が乗り移っている。実に気品高く身分も尊い様子をして、激しく泣く。僧たちはみな静かにしてそばで聞いているが、殿の上(倫子)は大将殿に薬湯などをあげて、まるで幼児のように抱かれて、
〈恐ろしいことになった〉
とたまらなく困っていらっしゃる。 物の怪が、殿(道長)に、
「近くへ寄りなさい」
と言うので、近づかれると、
「わたしは生きていた頃、愚か者とは誰からも思われなかった。そのわたしが軽々しい物の怪となって現れ、人間界でこのように話すのは、まったく未練がましいことのようですが、わが子が可愛いのはしぜんと大臣もおわかりのことですから申し上げるのです。この大将(頼通)を、生きていた頃、婿にしようと願い、なんとかしてなどと思ったのですが、命は果てて霊としてあるだけであるものの、空を走り飛んでも大将夫妻のあたりを片時も立ち去ることができず、わたしはそれほど罪障が深くはないのですから、どんなこともすべて見聞きしていることなのです。ところがこの大将を高貴な方の婿にしようとお考えなのを、ここ数日心中穏やかでなく、いくら成り行きに任せようと思ってみても、ひどく不安に思えてならないので、わたし自身で訴えようと思っていたところ、お気の毒なことにこの君(頼通)がこのように恐ろしい様子でいらっしゃるから、心配のあまりこんなことを言うのです」
とおっしゃると、大殿は(道長)は北の方(隆姫)の父の故中務宮(具平親王)の魂なのだとわかり、恐縮なさって、
「すべて本当にもっともなことですから、畏まって申し上げます。この件はけっしてあの子(頼通)の過失ではなく、またわたしの罪でもなく、しぜんの成り行きなのです」
と申し上げると、
「それでは、わが子を可愛いと思われるのか、思われるのか」
と何度もおっしゃるのは、今回の縁組のことを断念しろということだろう。大殿は、
「とにかくごらんになっていてください。おっしゃるとおりです」
と、道理にかなっていることを何度もお答えになるので、
「それでは安心して帰ることにしよう。いくらなんでも大臣は嘘はおっしゃらないと信じています。もし嘘なら恨むことになります」
とおっしゃって、それ相応の法文の尊い箇所を口ずさんでいらっしゃる。実際、その文言は間違いなく、霊の憑いた女房は、しばらく眠った後、正気に返った。 |
|
|
|
まだそんな時期ではないと誰もが油断しているところへ、女君が急に産気づいて苦しまれるので、これまで以上に祈祷の限りを尽くされるが、いつもの執念深い物の怪一つがどうしてもとり憑いて離れないので、尊い験者たちも、ただごとではないともてあましている。それでもさすがに激しく調伏されて、物の怪は辛そうに泣き苦しんで、
「祈祷をゆるめてください。源氏の大将に言いたいことがあります」
と言う。
「やはり、なにかわけがあるのだろう」
ということで、源氏の君を几帳のそばにお入れした。女君はこれが最期という様子なので、遺言でもなさるのではないかと、左大臣も大宮もその場を少し離れた。加持の僧侶たちが声を低くして法華経を誦んでいるのが実に尊く聞こえる。源氏の君が几帳の帷子を引き上げてごらんになると、とても美しく、お腹だけが高くなって寝ていらっしゃる姿は、夫でなくてもこれを見たら心が乱れるだろう。まして源氏の君が、
〈惜しい人だ、悲しい人だ〉
と思われるのも当然である。白い着物に、長いふさふさとした黒髪が束ねてそばに添えてある、その色合いがとても華やかで、こんなふうにとりつくろわない姿には可愛さもあでやかさも加わって
〈美しい方だったんだな〉
とごらんになる。源氏の君は女君の手を取って、
「悲しいよ。辛い目にあわせるんだね」
とおっしゃって、後は言葉にもならないで泣かれると、女君はいつもなら近寄りがたいこちらが気恥ずかしくなるような眼差しを、今はとてもだるそうに見上げてじっと見つめていらっしゃるうちに、涙がこぼれてくる。その様子をごらんになった源氏の君が、どうして愛おしく思われないはずがあろうか。
女君があまりに激しく泣かれるので、源氏の君は、
〈残して行く両親のことを考えたり、またわたしを見て名残惜しいからだろうか?〉
と思われて、
「なにごともそんなに思いつめないで。具合が悪いといってもそれほどでは。たとえどんなこと(死別すること)になっても夫婦は必ずあの世で巡り会えるのですから、きっとまた会うことができます。父上や母上なども、この世で深い縁のある親子は、あの世でも縁が切れないと言いますから、きっと会えると思ってください」
と慰められると、
「いえ、そんなことではありません。体がひどく苦しいので、調伏をしばらくゆるめてくださいとお願いしたのです。ここに来ようなんて少しも思っていないのに、物思いに苦しむ人の魂はほんとうに抜け出るものですね」
と親しげに言って、
なげきわび 空に乱るる わが魂を 結びとどめよ したがひのつま
(嘆きのあまり空に彷徨うわたしの魂を 下前の褄を結んでしっかりつなぎとめてほしい)
という声、感じは、女君ではなく別人になっている。源氏の君は不思議に思いながら考えてみると、それはまさしくあの御息所だった。あまりのことに、これまで人々がとやかく噂していたのを、つまらない者たちの言い立てることで、聞くにたえないと否定していらっしゃったが、実際に目の前で見て、
〈世の中にはこんなこともあるんだ〉
と気味悪くなられる。
〈ああ嫌だ〉
と思われて、
「そんなこと言うが誰なのかわからない。はっきりと言いなさい」
とおっしゃると、間違いなく御息所その人なので、驚き呆れるどころの話ではない。(葵) |
|
|
|
物の怪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 巻第四 みはてぬゆめ
一条殿は今は女院が領有していて、あの殿(為光)の女君たちは鷹司という所にお住まいだが、そこへ内大臣殿(伊周)がひそかに通っていらっしゃる。寝殿の上と三の君のことを申し上げたが、容姿も心も格別だということで、父大臣(為光)がことのほか可愛がられ、女子は容姿が第一ということで、大切にお世話なさっていたが、その寝殿の上に内大臣が通っていらっしゃったのである。
こうしているうちに、花山院がこの内大臣の四の君へ恋文を送り、意中をほのめかされたが、
〈とんでもないこと〉
と聞き入れられなかったので、たびたびご自身から鷹司をお訪ねになり、華やかに振る舞っていらっしゃったのを、内大臣殿(伊周)は、
「院のお相手は、まさか四の君ではなく、三の君だろう」
と推し量って、弟の中納言(隆家)に、
「この件は不安でしかたがない。どうしたらいいのだろう」
とおっしゃると、
「いや、ただわたしに任せてください。実に簡単なことです」
と言って、武者たちを二、三人連れて、花山院が、鷹司から月のとても明るい中を馬でお帰りになろうというところを、脅そうと思って、弓矢というものを射ることになったのか、花山院のお召し物の袖を矢が貫いたのである。
(中略)
巻第五 浦々の別
「太上天皇を殺そうとした罪が一つ、帝の母后を呪った罪が一つ、朝廷以外の人が行ってはならない大元帥法(だいげんのほう)を、私事として秘密裡に行った罪が一つ、それによって内大臣(伊周)を太宰権師(だざいのごんのそち)として配流する。また中納言(隆家)を出雲権守として配流する」
(中略)
巻第十二 たまのむらぎく
これということもなく月日が過ぎて行って、あの隆家中納言は、この頃目をひどく患われて、いろんな治療をなさったが、やはり物を見ることが難しく、今では世間づきあいもなさらず、情けない様子で籠っていらっしゃる。それにしても大殿(道長)なども、日頃碁や双六のよい遊び相手と思われ、好ましく待遇していらっしゃるので、とても心苦しく気の毒に思っていらっしゃる。(隆家は36歳とまだ若く、籠っていらっしゃるのは)残念なことで惜しまれてならない。
こうしているうちに、太宰大弐(平親信)が辞表を朝廷に提出したので、我も我もと後任を望んで騒ぐのだが、この中納言(隆家)は、
「どうなってもいい、申請して大弐になろうか」
と思い立って、それ相応の人に相談なさったところ、
「唐の人は目をとても上手に治療します。大弐になって筑紫に赴任なさり、治療させなさい」
と勧めるので、帝にも奏上なさり、中宮にもお願いしたところ、
〈とても心苦しいこと〉
と帝も思われ、大殿(道長)も、
〈中納言がほんとうにそう思うなら、ほかの人ではいけない〉
と思われ、中納言は大弐に就任なさった。
(中略)
こうして中納言(隆家)は陸路で、北の方は船で下向なさる。一品宮(脩子内親王)をとても気の毒に思われながら、このように遠国へと決心なさったのだから、宮としてもひどく悲しく思っていらっしゃるだろう。源中納言(経房)に一品宮のことをすべて頼んで下向なさった。しみじみと心にしみる悲しい世の中の様子である。出かけられる様子など、
「出雲への配流の時とは格段に違っている」
と、世の人が褒めるのも哀れである。 |
|
|
|
その年、朝廷では霊的な物の啓示がしきりにあって、不穏なことが多かった。三月十三日に、雷が鳴り稲光がして雨風が激しい夜、帝の夢に、桐壺院が、清涼殿の東庭の階段の下に立たれて、ご機嫌がひどく悪くて帝をにらみつけていらっしゃるので、帝は恐縮していらっしゃる。院が帝にお話しになることはいろいろと多い。源氏の君に関することであったのだろう。帝はたいそう恐ろしく、成仏できない院を気の毒に思われて、弘徽殿の大后にその話をなさると、
「雨などが降って空が荒れている夜は、思いこんでいることが夢に現れるものです。そう軽率に驚かれてはいけません」
と弘徽殿の大后はおっしゃる。
父院が睨まれた目と目を合わされたせいだろうか、帝は目を患われて耐え難く苦しまれる。物忌(斎戒)を、宮中でも大后の邸でも限りなくさせられる。
太政大臣(弘徽殿大后の父、朱雀帝の外祖父)がお亡くなりになった。亡くなられても当然の年齢なのだが、次々と不穏なことが自然と起こってくる上に、大后もどことなく患われて、日が経つにつれて弱っていかれるようなので、宮廷ではあれこれと嘆かれる。帝が、
「やはりあの源氏の君が、ほんとうに犯した罪もないのにあのように逆境に沈んでいるのなら、必ずその報いがあるだろうと思います。今はやはり元の位にもどしてあげましょう」
とたびたびじぶんの考えをおっしゃるが、
「そんなことをしたら、軽率だと世間から非難されるでしょう。罪を恐れて都を去った人を、三年も経っていないのにお許しになるようでは、世間の人もどんなふうに言い触らすでしょう」
などと、大后が固く諌められるので、帝がためらっていらっしゃるうちに月日が重なって、お二人の病気はそれぞれに重くなってゆく。(明石) |
|
|
|
病気、物の怪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 巻第十五 うたがひ
こうして(道長は)
「今はこれまで」
と院源(いんげん)僧都(そうず)を呼ばれて、剃髪なさった。北の方(倫子)も年来の望みだから、
「続いてわたしも出家を」
と思われ口にもなさるが、
「尚侍殿(憘子)を東宮へ参内させてから」
とおっしゃるので、とても残念なことと途方に暮れていらっしゃるのも実に悲しい。僧都が、髪を下ろそうとして、
「長い間、天下の柱石として、すべての人々の父として万人を育み、仏法の正しい教えをもって国を治め、非道の政もなく過ごしてこられたのに、最高の地位を去り、立派な家を捨てて、出家入道なさるのを、三世の諸仏たちは喜び、現世では寿命が延び、後生は極楽世界の上品上生にお上りになるだろう。三帰五戒を受ける人でさえ、三十六天の神祇、十億恒河沙(ごうがしゃ)の鬼神の護りがある。まして、真実の出家ではなおさらである」
などと、しみじみと尊く悲しいこと限りない。宮たちや、殿方も惜しみ悲しんでいらっしゃるのは、もっともで悲しくてたまらない。帝や東宮からの使者が絶えない。
この後、
〈どんなに病気が重くても治らないということはない〉
と思っていた通りに快方に向かった。物の怪どもは残念がり、悔しがること限りない。 |
|
|
|
源氏の院はお心の気強さもなくなり、じぶんながら、
〈すっかりぼけている〉
と思い知らされることが多いので それを紛らわすために、女房たちの部屋で過ごされる。仏の御前にはあまり大勢控えさせないようにして、心静かに勤行をされる。
〈紫の上とは千年も一緒に〉
と思っていらっしゃったのに、定められた別れとはいえ実に無念なことだった。今は
〈紫の上と西方浄土の同じ蓮の上に生まれたい〉
という願いを忘れることなく、後生のことをと、一途に思っていらっしゃる気持ちは揺るぎない。だが世間の噂を気にして出家に踏み切れないでいらっしゃるのは、情けないことである。
七日ごとの法事のことも、源氏の院がてきぱきと指示されることもなかったので、大将の君が引き受けて行われた。
〈今日こそは〉
と、院ご自身も出家を覚悟なさるときが多いが、いつの間にか月日は経ってしまい、(院は)夢のような気がするだけである。明石の中宮なども、お忘れになる時がなく、紫の上を恋しがっていらっしゃる。(御法)
|
|
|
|
習俗、出家
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 巻第二十四 わかばえ
関白殿(頼通)はこれまで子がいないのを嘆き、入道殿(道長)や、北の方(倫子)まで嘆いていらっしゃったが、故式部卿宮の御子の右衛門督(憲定)は、関白殿の北の方の伯父にあたり、その右衛門督(憲定)は、人から女のようだと思われていたところ、有国の宰相の娘に女の子を二人生ませたが、母も亡くなり、父君(憲定)はいろいろな女性の所へ通って、お亡くなりになったので、その女の子たちが今ではすっかり大人になられて、実に気の毒な暮らしをしていると聞かれて、関白殿の北の方(隆姫)は、
「他人ではないのだから」
と、引き取られて、二人とも関白殿の食事や、理髪などの世話をしているうちに、姉君は致仕の大納言(源重光)の子の則(のり)理(まさ)に縁づき、則理が尾張守になったので、尾張へ下向した。妹君には特に名前もつけないで、ただ住んでいる所をそのままに、対の君と呼んで使っているうちに、この君に関白殿がしぜんと親しくなっていった。情愛がある様子に、気に障るようなことが多々あるので、
「他人ならともかく、身内のものと」
などと、北の方の不快な様子に耐えられなくなって、対の君はしだいに実家に下がることが多くなっていたところ、前世の宿縁なのか、関白殿はほかのことなら北の方の意向に従われるのに、対の君とのことだけは譲らず、ともすれば外出のついでに立ち寄られる。昼なども隠れて出かけられるうちに、対の君が懐妊なさったのを、世間の人は、
「とても素晴らしい幸せな人」
と言ったり思ったりしている。この頃になって子を生むことに立ち会うので、関白殿はそれ相応の指図をなさっているうちに、
「お子がお生まれになります」
と大騒ぎするので、関白殿は極まりが悪く、ご自身ではお出かけにならないが、心配のあまり使者はしきりに差し向けられる。 |
|
|
|
「雪が小止みになった。夜が更けてしまう」
などと、さすがに北の方に遠慮して、それとなく外出を促して、それぞれ咳払いをしている。中将のおもとや、木工の君などが、
「悲しい夫婦仲ね」
などとため息をもらして話し合いながら横になっているが、北の方本人はじっと思いを静めていじらしく脇息に寄りかかって横になっていらっしゃる、すると、突然起き上がって、大きな伏籠の下にあった香炉を取って、髭黒の大将の後ろに近づいて、さっと香炉の灰を浴びせかける、人が払いのける暇もない、一瞬のことなので、大将は呆然としていらっしゃる。その細かな灰が目や鼻にも入って、ぼうっとしてどうしていいかわからない。灰をはらわれるが、あたりに立ちこめているので、衣装を何枚も脱がれる。正気でこんなことをされたのなら、二度と見向きもしないほど呆れはてたことだが、例の物の怪が、髭黒に北の方を嫌わせようとした仕業だと思うと、そばに仕えている女房たちも気の毒に拝見している。大騒ぎをして、衣装などを着替えられるが、おびただしい灰が鬢のあたりにもふりかかり、どこも灰だらけの感じがするので、善美を尽くしていらっしゃる玉鬘のところへ、このまま出かけるわけにもいかない。
〈狂ってるせいといえ、こんなに惨いことは今まで見たことがない〉
と大将は愛想も尽き、気味悪くなって、さっきの愛しく思っていた気持ちも消えてしまったが、
〈今 事を荒立てては、とんでもないことになるだろう〉
と気持ちを静めて、夜中になっていたが、僧などを呼ばれて物の怪調伏の加持祈祷をする騒ぎである。物の怪に取り憑かれた北の方が大声でわめいていらっしゃる声など、大将が嫌いになられるのも無理もないことである。(真木柱)
大将がこのように無理やり宮と夫婦のような顔をしていらっしゃるので、三条の北の方(雲居雁)は、
〈もうこれで終わりだろう〉
と思われ、
〈まさかこんなことにはならないと信じていたが、まじめな人が浮気をすると別人になってしまうと聞いていたのは本当だった〉
と、夫婦の関係がわかったような気がして、
〈もうこんなわたしを侮辱するような目にはあいたくない〉
と思われ、父の前太政大臣のところへ方違えを口実にしてお帰りになったが、ちょうど弘徽殿の女御が里下がりしていらっしゃったのでお会いになって、少しは辛い気持ちが晴れるような気がして、いつもは三条の邸に帰られても大勢の子供がいるので急いで帰られたが今回は帰ろうとはなさらない。大将殿もこのことを聞かれて、
〈やはりそうか、ひどく短気な性格だな、舅の前太政大臣も、また、大人らしく落ち着いたところがやはりなく、ひどく気短で、派手なことをされる人だから、
「気にくわない、顔も見たくない、声も聞きたくない」
などと言って、変なことをしかねない〉
と驚かれて、三条の邸にお帰りになると、雲居雁は姫君たちと、ごく小さい子を連れて行き、子供たちの何人かは残っていたので、その子供たちが父君を見つけて喜んでまつわりついたり、母君を恋しがってしくしく泣かれるのを、大将はかわいそうに思われる。
大将は何度も手紙を出して、迎えの使者をさし向けられるが返事もない。
〈こんなふうにものわかりの悪い軽はずみな妻だ〉
と、腹立たしく思われるが、舅の大臣の手前もあるので、日が暮れてからごじぶんで迎えに行かれる。雲居雁は弘徽殿の女御の寝殿にいらっしゃるということで、いつも里帰りで使われる部屋には、女房たちだけが控えている。若君たちは乳母と一緒にいらっしゃる。
「今になって若い娘のような付き合いをするのか、こんな子供たちを、あちこちにほったらかしにして、寝殿に遊びに行くなんて。わたしとは会わない性格だとはずっと前からわかっていたが、前世からの宿縁なのか、昔から忘れられない人だと思い、今はこのように手のかかる子供たちも大勢いてかわいいのだから、お互いに別れられるはずがないと信じていたのに、今度のような些細なことで、こんなことをしていいのか」
と、大将が女君が悪いようにひどく恨んでおっしゃるので、女君は、
「なにもかも、すっかり飽きられてしまったわたしですから、今さら、この性格が、なおるはずがないし、無理に辛抱することもないと思ってるの。みっともない子供たちは、捨てないでくだされば嬉しいけど」
とおっしゃる。大将は、
「ずいぶん素直な返事だな(皮肉)。結局は誰が悪く言われるのか」
とおっしゃって、無理に
「帰りなさい」
ともおっしゃらず、その夜は大臣邸で一人でおやすみになった。(夕霧) |
|
|
|
習俗 正妻との関係 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 巻第二十六 楚王のゆめ
若宮の湯殿の儀も終わって、尚侍殿(嬉子)のそばに忙しく横にしてあげるのを、殿(道長)も、尚侍殿と同じ気持ちでごらんになっている時に、尚侍殿が、
「こうして皇子が生まれたのを、どう思われますか」
とおっしゃるので、殿は、
「とても素晴らしいことと拝見しています」
とお答えになると、
「ですが、それが、どうしようもなく、ひどく気分が悪いのです」
とおっしゃるので、
「不吉なことを。そんなことはおっしゃるものではない」
とおっしゃる。尚侍殿はこの数日はしかにかかり、続いて物の怪が恐ろしかったので、ひどく衰弱なさり、食事もまったく召しあがらない。物の怪はその後影をひそめ、どなたも油断していた。恐ろしいと思われる一方では、皇子をお生みになるほどの前世からの宿縁なので、だれも心強く思われ気をゆるしていらっしゃった。
(中略)
辰の刻ごろに、子持ちの御前(嬉子)ひどくあくびをなさって、ほんとうに気分の悪そうな様子なので、御前に控えている女房は、
〈どうなされたのだろう〉
と拝見して、殿(道長)にこういう状態だと申し上げると、
「僧なども遠ざけたので、物の怪が祟るのだろう」
とおっしゃって、またそれ相応の僧たちがみな参上して、心を一つにして騒々しく読経する。
(中略)
尚侍殿(嬉子)はさらに耐えられない様子のまま、未(ひつじ)の頃になった。雨までが激しく降るので、雨音と僧たちの声が響きあう。世間では、
「臨終を迎えていらっしゃる」
と不吉なことまで言うので、宮々からの使者がしきりにあり、特に東宮からは頻繁にあるが、お返事もとどこおりがちである。殿(道長)は御簾の中で、子供にするようにじっと添い寝なさって、泣きながら抱いていらっしゃった。女房たちは誰一人気持ちのしっかりしている者はいない。殿の耳に届いていた尚侍殿(嬉子)のお声も、だんだんと消えていくようである。
〈ああ、なんということだ、情けないことだ〉
と思われるが、殿があらゆる手を尽くしていらっしゃるうちに、酉(午後6時頃)の頃に、蚊の鳴くような声になって弱っていらっしゃるので、御帳のまわりにあふれていた僧俗、上下、親しい人もそうでない人もすべて、願掛けをして額ずいて大声でお祈りをする。身分の低い者までが涙を流して、
「観音」
と申さない者はなく、みなが額に手をあててひたすら立居礼拝する。今は加持の声も、読経の声も聞こえず、
「観音」
と大声でお祈りするだけである。一人が一声申すのさえ、とても効験があるというが、まして多くの人が一心にお祈りするのだから、いくらなんでも回復しないことはないと思われる。だがとうとうお亡くなりになってしまわれた。御年は十九。殿は、
〈こんな悲しいことが、あまりにもひどい〉
と思われる。
(中略)
しばらくは枕もなにもかも同じままだったが、一夜も過ぎたので、ほんとうに情けなく思われながら、几帳や屏風などを逆様にしたりなどして、殿(道長)も北の方も、灯を取り寄せて、亡骸の近くにかかげてごらんになると、亡くなった方とは少しも見えず、白い着物で薄手のものを一揃いお召しになって、まだ腹帯もしていらっしゃった。乳房のとても美しい方で、硬くなるほど張っていらっしゃって、白く丸々として、可愛らしいようすで横になっていらっしゃっり、髪がとても多いのを、ゆるく結んで、枕もとに置かれているのは、ハッとするほどで、まるで眠っていらっしゃるようなので、殿も北の方もいまこそお泣きになる。
|
|
|
|
女君は時々返事をなさるが、やはりまだとても弱々しい。でも、もう助からないと思ったあの時の様子を思い出すと、夢のような心地がして、危篤状態であった時のことなども話してあげられるだがそれを話してると、あの息も絶えたようにしていた方が、一変してくどくどと語りだしたことが否応もなく思い出されて嫌な気持ちになるので、
「いやもう、話したいことはたくさんあるけど、まだ だるそうにしていらっしゃるから」
と言われて、
「薬湯を飲みなさい」
などと薬の世話までなさるのを、
〈いつのまに覚えられたのだろう〉
と、女房たちは感心している。
とても美しい人が、すっかり衰弱して、意識があるのかないのかわからないように横になっていらっしゃる様子は、とても愛らしく痛々しい。髪が一筋の乱れもなく はらはらと枕のあたりにかかっている姿は世に類のないほど美しく見えるので、
〈この数年、なにが不足だと思ってきたのだろう?〉
と、じぶんでも不思議なほど女君をじっと見続けていらっしゃる。
「院にも参上して、すぐに帰ってきます。今日のように、気楽に会うことができたら嬉しいけど、母宮がずっと付き添っていらっしゃるのに、わたしがそばにいたら失礼になるのではないかと遠慮していたのも辛かったから、やはり少しずつ気を強く持たれて、いつもの部屋で会いたいね。あまり子供じみていらっしゃるから、それもひとつの原因で、いつまでも快くならないのだよ」
などと話されて、とても美しい装束をつけて出かけられるのを、女君はいつもとは違って源氏の君をじっと見つめて見送りながら横になっていらっしゃる。
秋の司召(中央官庁の官吏の任免)がある日なので、左大臣も参内されると、ご子息たちもそれぞれに昇進をのぞんでいらっしゃり 父大臣のそばを離れられないので、みなが引き続いて参内された。
左大臣家の邸内が人が少なくなって ひっそりしていた頃、女君は突然、いつものように胸を咳きあげながら非常に激しく苦しまれる。宮中にいる人々に知らせるひまもなく、息が絶えてしまわれた。
どなたも足が地につかない状態で退出されたので、除目(任官)の夜だったが、こういうやむをえない病状の悪化のため、すべてがご破算になってしまったようである。
人々は大声をあげて騒ぐけど、あいにく夜中のことなので、比叡山の座主や、あちこちの僧都たちも呼び寄せることもできない。今はもう大丈夫だと安心していたのに、あまりにもひどい状態なので、左大臣家の人々は慌てふためいている。
方々から弔問の使者が続々とやってくるが 取り次ぐこともできないほど 邸内はごったがえしていて、人々の当惑ぶりは恐ろしいほどである。(葵) |
|
|
|
死の場面 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|